みなさんこんにちは!
鍼灸師オサダです。
今回は「疲れが抜けない人がやりがちな睡眠に影響を及ぼす生活習慣」ということで、睡眠にまつわる生活習慣をお話ししたいきたいと思います。
僕たち日本人の多くは睡眠不足とも言われていて、中々満足のいく睡眠が取れていない自覚をお持ちの方も増えてきています。
そうは言っても中々仕事の関係や家庭の事などで物理的に睡眠時間を長くすることは難しい‥
と、お悩みの方も多いと思います。
そこで今回はせめて睡眠の質は高めたいではありませんか!

ということで皆さんが意外にしがちな睡眠の質を下げてしまう生活習慣の話をしていきたいと思います!
早速みていきましょう!
そもそも睡眠は身体のリズムで出来ている!
まずこれが大前提の話になります。
というのも、よく睡眠の話になると
「なるべく早く布団には入るようにしているのよ」
という方も多くいます。
とても良い心がけだと思いますし、早く布団に入るに越したことはありません。
ですが、睡眠は身体のサーガディアンリズムといって、体内時計が大きく関係しています。
時差のある海外に行くと「うまく眠れなくなった」 「起きていられなかった」といったようにいわゆる時差ボケという言葉を聞いたことがあると思います。
この時差ボケは一過性(一時的)な”概日リズム睡眠障害”といわれ、体内時計にズレが生じている事を指しています。

これも人間のすごい所だと思いますが、個人差はあるものの時間が経つに連れて、その環境に合わせた体内時計が作られていきます。
話は睡眠のリズムについてに戻しますが、人間は基本的には朝に目が覚めて、夜になれば眠くなるといったようなリズムが作られています。
有名な話かもしれませんが、1日24時間なのに対して人間の体内時計は約24時間(約25時間という説が多い)といったように意外と大雑把なんですね。
そのちょっとしたズレを修正するのに役立つのが「光」とか「温度(体温)」とか「食事」といったものが役に立つわけです。
ここまでのお話しで、さては「光」とか「温度」とか「食事」などが体内時計を整える事に役立つし、反対にこれを上手に行えないと体内時計が乱れて、睡眠の質が下がるんじゃないかって思いましたよね?

そうです!
いわゆる睡眠を効率よく行うためには「生活習慣」というものが非常に重要になってきます。
睡眠の質を下げる習慣①|朝を適当に過ごしてしまう
多くの方と睡眠の話していると、
寝る前は‥
夜は‥
といったように夜の習慣についてお話ししてくれます。
ですが先ほどもいったように身体のリズムを考えた時には、夜の過ごし方だけでなく朝の過ごし方も凄く重要になってきます。
丁度先日までの年末年始のお休み期間中に、いつもより起きる時間が遅くなったという人も多くいると思います。
意外にこのリズムのズレがお休みがあけても解消されず、仕事の日の朝がよりだるく感じたり、シャキッとせずに生活に戻っている人もいるかもしれませんね。
もちろん色々な要素はあると思いますが、朝スッキリ起きれない人は体内時計のズレから、睡眠の質が悪くなっている可能性も考えられます。
反対に夜の睡眠の質を高めるためには朝しっかり起きるという事が質の良い睡眠につながります。
ですから、朝は適当に過ごしてはいけません。

睡眠の質を下げる習慣②|日光不足・ライト浴びすぎ問題
次に現代人に多い、光と身体のリズムのズレについてです。
これまでにもブログにしている部分でもありますが、身体のリズム作りには光は凄く大きな要素となります。
日光不足は→日中
ライトの浴びすぎは→夜
で多い傾向で、一言で言えば光の刺激が「メリハリがない」という事です。
元々これだけ電気や光がなかった時代では、光の供給源は『太陽』か『火』だったわけです。
太陽の光を浴びる事は、日光浴とも言われ様々な健康効果が認められています。
仕方ないといえば仕方ないですが、多くの人は日の光が上がっている時に室内で仕事をしたり、お休みの日でも直接日光に当たる機会が減っています。

またガラス越しの日光の光は、日光浴によって得られるメリットが減ってしまうとも言われています。
そう考えると日光を浴びる時間って結構少なくないですか?
それに反するように、室内の光や、液晶などのブルーライトを浴びる時間は増えており、まさに昼夜の光によるメリハリが減ってしまっています。
スマホやPCのような光は悪という解釈になりがちですが、実はそうとも言い切れない部分もあるみたいで、太陽にもブルーライトは含まれているし‥といったような意見や、ブルーライトでも光刺激によって幸せホルモンと呼ばれるセロトニン生成が促されるという方もいます。
(セロトニンは光刺激によって分泌が活性化される)
僕自身も夜にはブルーライトカットメガネを使っていますが、これでは対策にはならないというデータもあるみたいです。(僕はつけている方が少し楽な気がするので夜は変わらず必ずつけています。)
色々と意見があるのを踏まえても、僕自身は光刺激というもののメリハリがなくなっている事が問題だと感じていて、セロトニン生成に光が重要とは言いましたが、では常に浴び続ければ分泌が活性化されるのでは?と思うかもしれませんよね。
ただそこはやっぱり僕達は人間ですから、機械のようにA=Bではいかない事もあると思います。
いつしか刺激に対する慣れというものが必ず出てきて分泌量は減っていくと思います。
やっぱり基本的には日中に光を浴びて、夜は控えめにする。これが身体のリズムを作る上では鉄則かと思います。

睡眠の質を下げる習慣③|不規則な食生活
ここも重要なポイントです。
食事に関していうと多くの場合が食べる内容について語られる事が多いと思います。
(もちろん食べる内容も重要です!)
ですがこのリズムという意味でも大事になってくるのは、食べる時間や回数についても重要です。
以前”食事改善何から始めたらいい?~知っておきたい自分の現在地~”というブログを書いていますが、ここでも食生活と身体のリズムについても少し触れています。
食事をする事によって胃、肝臓、膵臓、皮膚、血管などを中心に、入ってきた栄養素、内臓の働きが体内時計のリセットに役立ちます。
またこの体内時計については2017年にノーベル生理学・医学賞で話題にもなりましたが、1番重要なのは朝食と言われています。

睡眠の質を下げる習慣①でもお話したように“朝の過ごし方を適当にしてしまう”には個人的には朝食も含まれていて、朝食を食べない。偏ってしまっている。やっぱりこれでは、身体も目覚めてきません。
特に朝食ではバランスを意識して摂れるといいでしょう。
今や朝食は4人に1人が食べないと言われており、その理由も「お腹が空かないから」とか「朝時間がない」といった理由です。
ここにも夜の過ごし方や、睡眠の問題が背景に隠れている事が多く、寝る直前ご飯を食べる習慣があったりする事が朝のお腹の空かない原因になっていたりします。
つまりここでも生活習慣が関与しているという事です。
朝食べた方がリズムが作られやすい事を考えてみると、朝の時間確保する+お腹が空く状態を作る→夜しっかり眠る→食べる時間や食べる物の見直し(夜も朝も)→その結果睡眠の質も変わっていく。
こういった流れが作れれば良いですね。
睡眠の質を下げる習慣④|運動不足
運動不足は筋力の低下や身体の機能が低下するだけではなく、体内時計にも大きく関係しています。
運動によって分泌が促進されると言われているホルモンの中に
・成長ホルモン
・セロトニン
この2つが挙げられます。

他にもありますが今回はこの2つに着目していきます。
皆さんは子供の頃
・日付をまたぐ前に寝なさい!
・寝る子は育つ!
みたいな話を言われた事はありませんか?
これも今考えてみればこの成長ホルモンとか、身体のリセット、休息の事を考えて言われていたとよくわかります。
成長ホルモンは、その名の通り身体の成長に役立ちますが、他にも身体の回復にも役立ちます。
そしてこの成長ホルモンは、深い睡眠時に分泌が高まると言われています。
さらに以前こちらのブログで紹介している”幸せホルモン セロトニンと睡眠ホルモン メラトニン”についてですが、睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンはセロトニンを材料にして作られます。
セロトニンなくして睡眠ホルモン メラトニンが作られないのでセロトニンはすごく重要なホルモンです。
先に紹介している光とセロトニンの関係に加えて、運動不足が重なるとよりセロトニンの生成から分泌が行われなくなってしまい結果的には睡眠の質を下げている可能性もあります。
ですので話を戻すと結局朝に散歩などの軽い運動でいいからしたほうが良いと言われるのは、身体の目覚めを利用して体内時計のリズム作りに役立つからだと考えています。
そしてこれらのホルモンの面白い所は、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールとは相反するように分泌量が増加します。
コルチゾールはセロトニンの分泌を妨げる他、夜になると分泌が高まるメラトニンに対してコルチゾールは分泌が減少していきます。(明け方〜日中の分泌が高いとされている)
また成長ホルモンの分泌時にはコルチゾールの分泌も減ります。
難しい話は置いておいて運動時にはセロトニンや成長ホルモンの分泌が促進されることで身体のリズムを作る土台ができるようなイメージで良いと思います。
運動の工夫を行う事が重要なので、ハードな運動とかきつい筋トレではなく自分に適したことから始めてみましょう!
睡眠の質を下げる習慣⑤|寝る直前の色々
ここで最後に寝る直前の色々について話します!
寝る前の習慣が重要な事は言うまでもないかもしれませんが、いくつか睡眠の質を下げてしまう例を挙げてみましょう。
・寝る直前の液晶の見過ぎ
・寝る直前の入浴
・寝る直前の食事
・寝る直前の運動
です。
これらは気が付かぬうちに行っている人もいるかもしれません。
寝る直前の習慣として大事なのは
リラックスした身体づくりです。
液晶、食事、運動が直前に行うのは良くないというイメージがあるかもしれませんが、実は寝る直前の入浴も睡眠の質を下げてしまいます。
質の良い睡眠のためには深部体温が下がって、表面体温(四肢末端の体温)が上がる必要があります。
(眠たい赤ちゃんの手があったかくなる感じです)
寝る直前の習慣も日中の習慣と合わせて見直してくださいね!

まとめ
今回は①〜⑤の睡眠に影響を及ぼす生活習慣を紹介しました。
5つを通して最初に話した身体のリズムを中心に紹介しました。
ちなみにコーヒーなどに含まれるカフェインは体内から完抜けるのに約9~10時間かかると言われています。(諸説あり)
カフェインをとっても寝れるし‥!
と言う方もいますが、カフェインに含まれる覚醒作用は寝れていたとしても体内では反応しているので睡眠の質には影響しています。
ですのでカフェインの摂取は午前中からお昼過ぎ(15時くらいまで)にしておくのが良いでしょう!
とはいえ皆さんそれぞれに生活がありますから全てを一気に実現させるのは難しいかもしれませんね。
小ネタとして知っておくだけでちょっと意識が変わる!それでも十分だと思います。
ぜひ参考により良い毎日に役立ててください。
今回も最後までありがとうございました!
【関連動画】

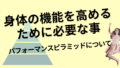
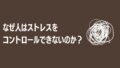
コメント